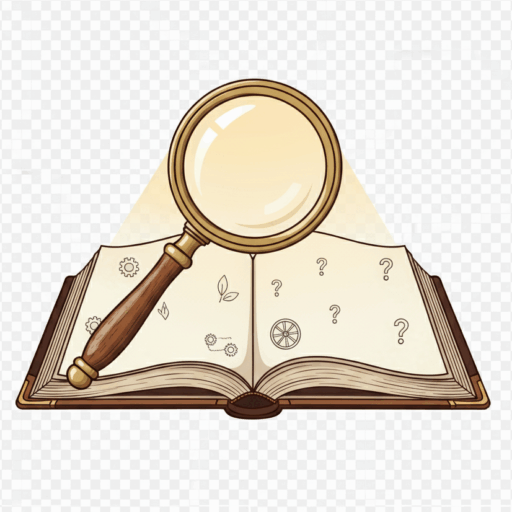最近、メディアや論壇で「積極財政」という言葉を耳にしない日はない。曰く、「不況なのだから、政府が国債を発行してでも財政出動をすれば経済は成長する。これは経済学の教科書に書いてある常識だ」と。その力強い響きは、長引く停滞に喘ぐ人々にとって、一筋の光明のように聞こえるのかもしれない。
私も若い頃、その「教科書」を手に経済学を学んだ一人だ。IS-LM分析という美しいモデルを前に、財政政策がIS曲線を右にシフトさせ、国民所得を増大させるメカニズムに知的な興奮を覚えたものだ。
だが、その主張を「今、現代」において聞くたびに、ある種の既視感とそれ以上の深い懸念を抱かざるを得ない。それは、古い海図を頼りに、全く異なる海流と天候の海へ乗り出そうとしているような感覚だ。
積極財政派の議論から決定的に抜け落ちている視点、それは彼らが依拠する「教科書」が描く世界と、我々が生きる現代日本との間に横たわる、致命的なまでの前提条件の違いである。
私が学んだ教科書の経済モデル、特にIS-LM分析が暗黙のうちに前提としていたのは、「労働力は潤沢に存在する」という世界観だった。それは、ケインズが大不況の惨禍を目の当たりにした時代、あるいは戦後の人口ボーナス期のように、社会に「働きたいが、働く場所がない」という非自発的失業者が溢れていた時代の写し絵だ。このモデルの中では、労働市場は分析の枠外に置かれ、物価も一定と仮定される。需要さえ喚起すれば、供給はそれに自動的に追随する。なぜなら、需要に応えるための「人手」は常にそこにいる、と考えられていたからだ。
しかし、私たちが今いるのは、その前提が根底から崩壊した世界である。生産年齢人口は1990年代をピークに減少の一途をたどり、今やあらゆる業界で人手不足が叫ばれている。これは一時的な景気循環ではなく、数十年単位で続く不可逆的な構造変化だ。教科書の世界では「余っていた」はずの労働力が、現代日本では最も希少な経営資源となった。
この供給側の制約を無視して、需要刺激策だけを唱えることの危うさは、より包括的なAD-AS分析(総需要・総供給モデル)の視点に立てば明らかだ。経済を一つの工場に例えてみよう。
教科書が想定する不況とは、工場に稼働していない生産ラインと、手持ち無沙汰な従業員が大量にいる状態だ。この時、政府が大規模な注文(財政出動)を出せば、工場は喜んで生産ラインを動かし、従業員を働かせ、生産量を増やすことができる。注文が増えた分だけ、素直に生産高(実質GDP)が伸びる世界だ。
一方で、現代日本という工場は様相が全く異なる。多くの従業員が定年退職し、新しい働き手は入ってこない。生産ラインはあっても、それを動かす人間が足りない。
この状態で政府が同じように大規模な注文を出したらどうなるか。工場は限られた従業員で注文をこなすため、残業代を払い、他社から高い給料で人を引き抜こうとするだろう。結果、生産量はさして増えないのに、人件費というコストだけが膨れ上がり、製品価格に転嫁される。これが、実質的な成長を伴わないインフレの正体だ。
積極財政派の議論は、この工場の「中の事情」、すなわち供給能力の制約を驚くほど軽視している。彼らは、アクセルを踏みさえすれば車は加速すると信じているようだが、肝心のエンジン(生産性)が縮小し、ガソリン(労働力)も不足している現実が見えていない。この状態でアクセルを踏み込めば、エンジンが焼き付く(投入コストに対して生産性が上がらない)か、高いガソリンを無駄遣いする(悪性インフレを招く)だけで、終わるだろう。
もちろん、財政支出の全てを否定するものではない。だが、その有効性は「何に」支出するかにかかっている。問われるべきは、その支出が希少な労働力を補う生産性向上に繋がるのか、あるいは人手不足をさらに深刻化させるだけの需要喚起に終わるのか、という点だ。
20世紀の人口増加社会で描かれた古い地図は、21世紀の人口減少社会という未知の航海にはもはや役に立たない。我々がまずなすべきは、羅針盤が指し示す「人口動態」という厳然たる事実を直視し、この新しい海を乗り切るための、全く新しい海図を描き始めることではないだろうか。