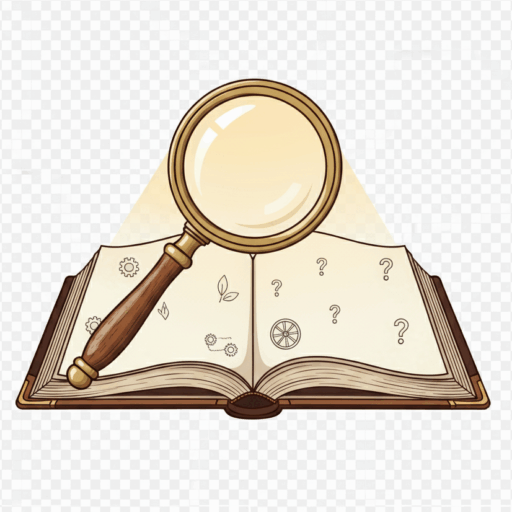永田町がにわかに騒がしくなっています。
石破総理が辞任を表明し、自民党の次のリーダー、すなわち総裁を選ぶ選挙のニュースが連日メディアを賑わせています。テレビの画面には候補者の顔が並び、「次の総理は誰か」という話題で持ちきりです。
ここで、多くの方が素朴な疑問を抱くのではないでしょうか。
「あれ?選挙で自民党は過半数を割ったはずなのに、なぜ次の総理も自民党から選ばれるのが当たり前のような話になっているのだろう?」
確かに、衆議院も参議院も与党は過半数に届いていません。それならば、野党が力を合わせて自分たちのリーダーを総理大臣に、という展開があってもよさそうです。
しかし、現実はそう単純ではありません。そこには、私たちが学校で習った「多数決」の、少しややこしい、しかし重要なルールが関係しているのです。
日本の総理大臣は、国民が直接選ぶわけではなく、国民の代表である国会議員が国会で投票して選びます。そして、もし衆議院と参議院で違う人が選ばれた場合は、必ず衆議院の投票結果が優先されるという絶対的なルールがあります。ですから、次の総理が誰になるかは、ひとえに「衆議院で誰が一番多くの票を集めるか」にかかっているのです。
現在の衆議院の議席を見てみましょう。自民党と公明党を合わせても、過半数には少し足りません。
では、なぜ野党が勝てないのか。それは、野党が一枚岩ではないからです。
これを、ある学校のクラス対抗のイベントだと想像してみてください。一番人数の多いA組(自民党)は、団結して「A組のリーダー」をイベントの総責任者に推薦します。一方、B組(立憲民主党)やC組(日本維新の会)、D組(国民民主党)などは、それぞれが「うちの組のリーダーこそがふさわしい」と主張し、お互いに譲りません。いざ投票となると、A組の候補者にはA組全員の票が集まりますが、他の候補者にはB組、C組、D組の票がバラバラに入ってしまいます。
結果として、過半数を取れなくても、A組の候補者が一番多くの票を集めて当選する、というわけです。
今の国会はまさにこの状況です。自民党は次の総裁を総理候補として結束して投票しますが、野党は立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などがそれぞれ自分たちの党首に投票するため、票が割れてしまうのです。
「なぜ野党は協力しないのか」と不思議に思うかもしれません。もちろん、彼らも協力の必要性は分かっています。しかし、安全保障や憲法、経済政策といった国の根幹に関わる考え方が党ごとに大きく異なり、「誰をリーダーにするか」という点で簡単には一致できないのです。無理に手を組んで政権を獲っても、その後の運営で意見が対立してすぐに空中分解してしまうことを、彼らは過去の経験から学んでいます。
こうして、おそらく次の総理大臣も、自民党の新総裁が就任することになるでしょう。
しかし、この話には大切な続きがあります。そうして誕生する新政権は、決して「強い政権」ではありません。何しろ、国会で過半数を持っていないのですから。法律を一つ通すにも、予算を決めるにも、野党の誰かに「お願いします、賛成してください」と頭を下げなければなりません。
つまり、野党は総理大臣のポストこそ取れないかもしれませんが、政権の運営に大きな影響力を持つ「キャスティングボート」を握ることになります。これからの日本の政治は、自民党が一方的に物事を決める時代から、野党との地道な交渉と妥協が不可欠な状態が継続すると考えられるのです。
自民党の総裁選は、結果的に次の総理を決める重要なイベントになるでしょう。しかし、その裏側にある国会の勢力図と、そこから生まれる新しい政治の力学に目を向けてみると、私たちの国のこれからが、より深く、面白く見えてくるのではないでしょうか。
また、このような困難な状況からも、その政権が長く続くということもなかなか見通せないと思われます。野党も大連立というリスクを負って首相の座を手に入れても、得られるリターンが短命な首相の座だけでは、動かないほうが良いと考えるのが合理的判断のように思えます。しかし、政治は合理的に動かないのも世の常なので、果たしてどういう結末になるのでしょうか?