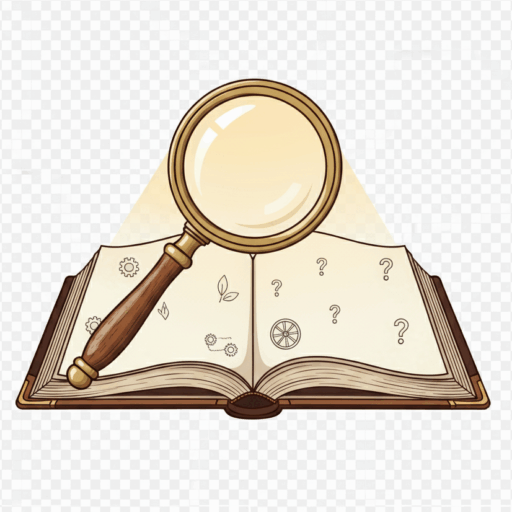今回のJICA「アフリカ・ホームタウン計画」を巡る一連の騒動は、国際協力の現場で起こりうる、コミュニケーションの難しさを象徴する典型的な事例と言えます。結論から申し上げると、この計画は移民政策とは全く関係なく、JICAがそのような政策に関与する権限も意思も一切ありません。
ではなぜ、これほど大きな誤解が生まれてしまったのでしょうか。
その根本的な原因は、JICAが良かれと思って選んだ「ホームタウン」という言葉が持つ、日本語と英語の「温度差」にありました。
1. 「ふるさと」に込めた想いと「Hometown」が招いた誤解
日本人が「ふるさと」という言葉を聞くと、多くの場合は「心の拠り所」や「懐かしい場所」といった、情緒的で温かい響きを感じ取ります。法的・行政的な意味合いはほとんどなく、あくまで象徴的な言葉です。JICAはこの計画に「ホームタウン」と名付けることで、アフリカの国々と日本の地方都市が、まるで第二の故郷のように親密な関係を築いてほしい、という願いを込めたのでしょう。
しかし、この「ふるさと」の直訳である英語の「Hometown」は、海外、特に政府間の公式な発表で使われると、全く違うニュアンスで受け取られてしまう危険性を孕んでいました。情緒的な意味合いが薄れ、「(国民が住むべき)本拠地」「(特別な権利が与えられる)指定都市」といった、より具体的で実利的な意味合いで解釈される余地が生まれてしまったのです。
この言葉の選び方が、最初の、そして最大のボタンの掛け違いでした。
2. 期待のズレが生んだ「誤報」の連鎖
日本側が「心の繋がり」を意図して使った「Hometown」という言葉を、パートナー国側は「具体的な機会」と受け取りました。
- ナイジェリア政府の発表: ナイジェリア政府は、自国民の期待に応える形で「日本政府が、木更津市で働くための特別なビザを用意する」と発表してしまいました。これは、JICAの意図を完全に超えた「過剰な期待」が生んだ誤報でした。
- タンザニアのメディア報道: タンザニアの新聞は「日本が長井市をタンザニアに捧げた(dedicate)」と報じました。英語の “dedicate” は文脈によっては「捧げる」とも訳せますが、この見出しだけが切り取られ、日本では「日本の領土が譲渡される」という、あり得ない陰謀論の証拠として拡散されてしまったのです。
JICAは、こうした発表がなされる前に、相手国政府と「ホームタウン」という言葉の定義や事業の範囲について、認識を完全にすり合わせておくべきでした。この事前のコミュニケーション不足が、誤解が生まれる隙を与えてしまったのです。
3. JICAの権限と役割の根本的な事実
ここで最も重要な事実を整理します。今回の騒動で「JICAが移民政策を進めている」という批判がなされましたが、これは制度的に不可能です。
- JICAにビザ発給の権限はない: JICAは、政府開発援助(ODA)などを実施する独立行政法人であり、国際協力の専門機関です[3]。しかし、外国人の入国に必要な査証(ビザ)を発給する権限は一切持っていません。ビザの発給は、海外にある日本の大使館や総領事館、つまり外務省の専管事項です。
- JICAは移民政策を決定できない: そもそも、どのような外国人を、どのような条件で受け入れるかという移民・在留政策は、国会で法律(出入国管理及び難民認定法)によって定められ、法務省の外局である出入国在留管理庁が管理しています。JICAは、政府が決定した政策を実行する一機関に過ぎず、独自の判断で移民を受け入れたり、在留資格を創設したりすることは絶対にできません[11]。
結論:JICAが本当に犯した間違いとは
JICAが犯した間違いは、「移民政策を秘密裏に進めようとした」ことでは断じてありません。本当の間違いは、以下の2点に集約されます。
- 文化的な想像力の欠如: 「ふるさと」という日本的な情緒を持つ言葉が、海外でいかに具体的・実利的に解釈されうるか、という点への配慮が欠けていたこと。
- 事前のコミュニケーション不足: 計画を発表する前に、パートナーとなる国々と事業の目的や限界について徹底的に共有し、誤解の余地のない共通認識を形成するプロセスを怠ったこと。
善意から始まった国際交流が、たった一つの言葉の選び方とコミュニケーション不足によって、本来の目的とは全く関係のない「移民問題」という大きな社会不安の受け皿になってしまいました。これは、JICAにとって、そして今後の日本の国際協力にとって、重い教訓を残した事例と言えるでしょう。