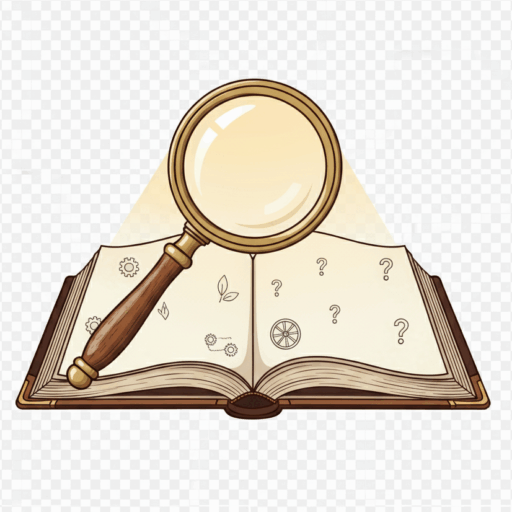書斎の窓から見える欅の葉が、日ごとにその色を深くしていく。季節の移ろいは穏やかで、決まった順序でやってくるというのに、人の世はいつも、どこか騒がしい。近頃、ふとしたきっかけで、遠い昔のドイツで独裁者となった男と、現代日本の新しい政党とが、並べて語られているのを耳にした。ヒトラーと、参政党。あまりに突飛な組み合わせに、はじめは少し驚いたが、なぜそうした言葉が出てくるのか、私なりに少しばかり思いを巡らせてみたくなった。誰かを断罪するためではなく、ただ、この時代の空気の中に漂うものを、静かに見つめてみたいと思ったからだ。
遠い日の熱狂を思う
私が生まれるよりずっと前の話だが、かの独裁者は、その弁舌ひとつで国民を熱狂させ、ついには国家の頂点に上り詰めたという。教科書で知るその歴史は、どこか遠い世界の出来事のように感じられる。しかし、当時の人々の心の内を想像してみると、また違った景色が見えてくる。
第一次大戦に敗れ、経済は混乱し、国民が誇りを失いかけていた時代。そんな不安のただなかに、彼は現れた。その言葉は、驚くほど単純で、力強かったという。「悪いのは彼らだ」「我々は偉大なのだ」と。複雑で先の見えない現実を前に、これほど分かりやすい物語が、どれほど人々の心を慰め、勇気づけたことだろう。
彼は、演説というものを一種の劇場空間のように演出したらしい。人々が仕事で疲れ、理屈よりも感情が動きやすい夕暮れ時を選び、聴衆が静まり返るまでじっと待ってから、静かに語り始め、やがて嵐のような熱弁で締めくくる。その様子は、当時普及し始めたラジオや映画という新しい道具に乗って、ドイツ中の家庭に届けられた。鉤十字の旗がはためく巨大な党大会の映像は、個人を巨大な共同体の一部であるかのように感じさせたことだろう。
今から思えば、それは恐ろしい熱狂の始まりだった。しかし、その渦中にいた人々にとっては、希望の光に見えたのかもしれない。人の心とは、かくも脆く、そして力強い言葉に惹かれるものなのだろう。
現代の辻説法に耳を澄ます
翻って、現代の日本。駅前や交差点で、YouTubeの画面の中で、参政党の人々が熱心に語りかけている。これもまた、一種の辻説法のようなものかと、足を止めてみることがある。
彼らが掲げる「日本人ファースト」という言葉。この言葉に、ある種の人々が強く惹かれるのはなぜだろうか。おそらく、そこには「失われた30年」と呼ばれる長い経済の停滞があり、自分たちの声が政治に届いていないという、深い無力感や疎外感があるのかもしれない。
彼らもまた、分かりやすい「敵」を指し示す。それはかつてのような特定の人種ではなく、「グローバリスト」や「腐敗したエスタブリッシュメント」といった、もっと漠然とした存在だ。そして、「眠りから覚めよ」「自分たちが主人公になるんだ」と、人々の主体性に訴えかける。これもまた、複雑な社会を単純な構図で理解したいという、人間の自然な心の働きに応えるものなのだろう。
彼らの言葉は、テレビや新聞といった古いメディアを飛び越えて、YouTubeを通じて直接、共感する人々の元へと届けられる。同じ考えを持つ人々がオンラインで繋がり、互いの意見を肯定し合うことで、その思いはさらに強固なものになっていく。これもまた、時代の流れというものか。
似て非なるもの、水面に映る影
こうして二つの運動を並べてみると、確かに人の心をつかむ手法には、時代を超えた共通点があるように思える。不安を共有し、敵を示し、単純な言葉で希望を語る。これは、人を動かすための、古くからある定石なのかもしれない。
しかし、私は思うのだ。この二つを安易に重ね合わせることには、大きな危うさが潜んでいると。決定的に違うのは、その手法の先に何を目指しているかだ。ナチスは、その初期から暴力的な組織を抱え、民主主義の仕組みそのものを内側から破壊することを目的としていた。権力を握るや、たちまち一党独裁へと突き進んだ。
一方、参政党は、現行の民主主義のルールの中で、議席を得て政策に影響を与えようとしている。その主張がいかに過激であっても、体制そのものの転覆を綱領に掲げているわけではない。この一点を見誤ってはならない。水面に映る自分の影を見て、怪物と見間違えるようなことはしたくないものだ。
なぜ、声は響くのか。私たちの足元を見つめる
むしろ、私たちが考えるべきは、なぜ、こうした声が人々の心に響くのか、その土壌についてではないだろうか。
いつの頃からか、私たちは政治というものをどこか遠いものと感じるようになってしまった。繰り返される政治とカネの問題にうんざりし、メディアの報道にも素直に頷けなくなっている。この根深い不信感が、既存の仕組みの外側に、新しい答えを求めさせるのかもしれない。
そして、私たちの多くが、この国の未来に漠然とした不安を抱えている。経済は長く停滞し、かつての輝きは失われたように感じる。そんな閉塞感が、失われた栄光を取り戻そうという勇ましい物語に、耳を傾けさせるのではないか。
手の中にあるスマートフォンを覗けば、アルゴリズムが私の好みに合わせた情報ばかりを届けてくれる。心地よい世界に浸っているうちに、いつしか自分とは異なる意見から遠ざかってしまう。この便利な道具が、知らず知らずのうちに、社会の分断を深めているとしたら、それはなんとも皮肉な話だ。
風に揺れる葦として、考える
では、私たちはどうすればいいのか。声高に誰かを批判し、論破したところで、おそらく何も変わりはしないだろう。
ふと、哲学者ハンナ・アーレントが語った「悪の陳腐さ」という言葉が心に浮かぶ。歴史を揺るがすほどの巨大な悪は、特別な怪物によってではなく、考えることをやめてしまったごく普通の人々によって引き起こされる、と。
だとすれば、私たちにできることは、ささやかだが、たった一つしかないのかもしれない。それは、自分の頭で「考える」ことを、決してやめないということだ。
流れてくる情報を鵜呑みにせず、少し立ち止まって「本当だろうか?」と自問してみる。面倒でも、自分とは違う意見に、少しだけ耳を傾けてみる。結論を急がず、白か黒かで割り切れない灰色の部分を、そのまま受け入れてみる。
あるいは、もっと身近なところに目を向けるのもいい。地元の商店街で買い物をし、地域の活動に顔を出してみる。顔の見える関係の中で交わされる何気ない会話が、凝り固まった心を少しずつ解きほぐしてくれることもある。
この騒がしい時代にあって、風に揺れる葦のように、しなやかに、しかし深く根を張って、ただ静かに考え続けること。それこそが、私たちが保つべき、ささやかで、しかし最も大切な態度なのではないだろうか。そんなことを、つれづれなるままに考えている。