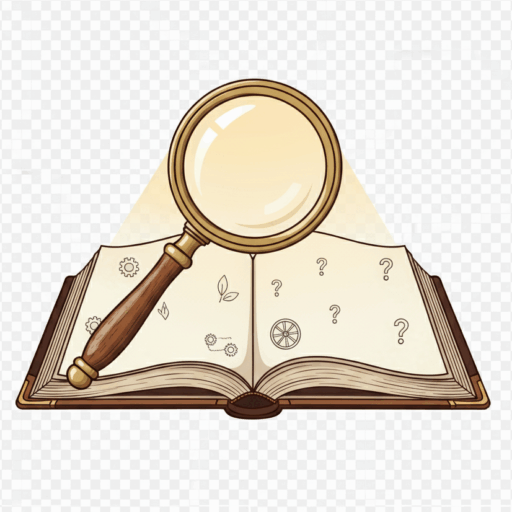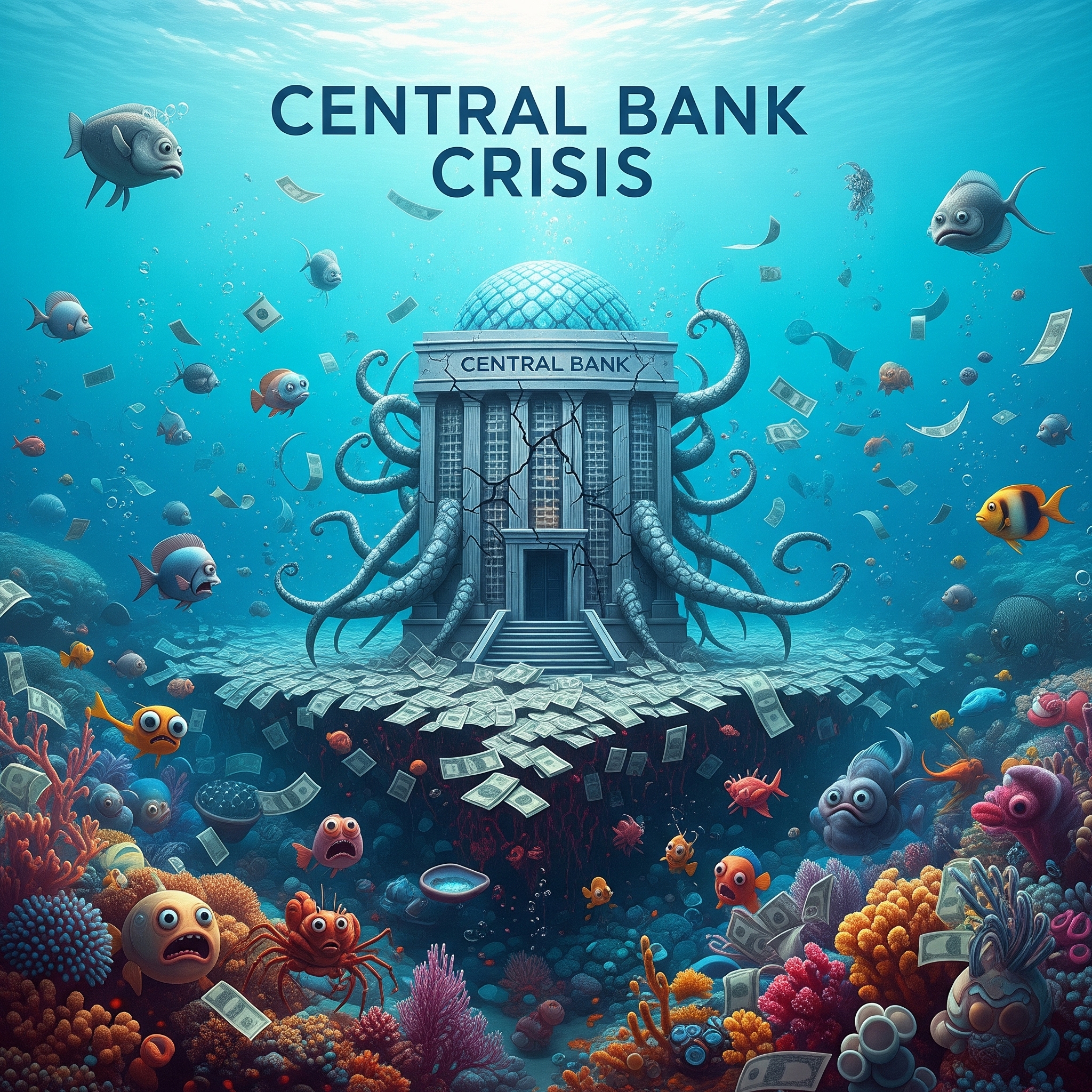序章:ゼロポイント
2025年8月、海洋国家「ヒノモト群島国」の首都は、蒸し暑い静寂に包まれていた。だが、その静けさとは裏腹に、中央銀行の重厚な石造りの建物の中では、見えざる嵐が吹き荒れていた。
政策分析官であるイシカワ・カイトのデスクには、二つのファイルが置かれていた。どちらも、国の運命を左右する選択肢を示している。
政策金利は0.5%。市場が「損益分岐点」と囁く、運命の数字だ。
ここから一歩でも金利を引き上げれば、中央銀行は自らの血を流し始める。「通貨発行損」という名の、構造的な赤字の発生である。過去十数年にわたる「異次元の緩和」という壮大な金融実験が、中央銀行自身を巨大な罠にかけたのだ。
カイトは窓の外に目をやった。街は平穏に見える。しかし、この平穏は、ゼロ金利という麻薬によって保たれてきた砂上の楼閣に過ぎないことを、彼は知っていた。
そして今、その麻薬が効かなくなりつつあった。
第一章:二つの道
カイトは一つ目のファイルを開いた。表紙には「シナリオA:正常化への道」と記されている。
それは、中央銀行が財務的損失を覚悟の上で、物価安定という本来の責務を全うするために利上げを断行する、苦難の道だった。
彼の脳裏に、その選択がもたらす未来が映像のように浮かび上がった。
「シナリオA:正常化への道」の未来
市場の混沌
利上げが発表された瞬間、為替市場では自国通貨「ウヲ」が急騰するだろう。長年のウヲ安に苦しんできた輸入業者たちは安堵のため息をつくかもしれない。
しかし、その安堵は長くは続かない。利上げが進むにつれ、中央銀行の損失拡大が報じられ、その財務への信認が揺らぎ始める。ウヲは乱高下を繰り返し、かつての安全資産の地位を失い、投機の対象と化す。
国債市場では、中央銀行という最大の買い手を失ったことで価格発見機能が回復する一方、誰もがリスクを再評価し始める。
海外投資家は、高い利回りに惹かれる者と、この国の財政リスクを恐れて逃げ出す者に二分され、市場は極度の不安定に陥る。
実体経済の痛み
金利のある世界への回帰は、経済の隅々にまで痛みを強いる。
変動金利で資金を借り入れてきた中小企業は、返済負担の急増に耐えきれず、次々と倒産していくだろう。住宅ローンを抱える家庭では、月々の返済額が跳ね上がり、消費は凍りつく。
政府もまた、国債の利払い費の増大に苦しみ、社会保障や公共サービスが削減される。経済は深いリセッション(景気後退)に陥る。
それは、外科手術のような道だった。病巣を切り取るためには、激しい痛みを伴う。しかし、その先には正常な経済への回復という希望があるかもしれない。
次に、カイトは二つ目のファイルに手を伸ばした。「シナリオB:現状維持の道」。
これは、中央銀行が自らの財務を守ることを優先し、追加利上げを躊躇する道だった。
「シナリオB:現状維持の道」の未来
静かなる崩壊
市場は中央銀行の不作為を「政策の麻痺」と見なすだろう。ウヲは再び下落を始め、そのスピードは加速する。
それはもはや輸出企業を潤す「良いウヲ安」ではない。国の信認そのものが失われる中で進む「悪いウヲ安」だ。
輸入されるエネルギーや食料品の価格は高騰し続け、国民の生活を直接圧迫する。
スタグフレーションの罠
経済は停滞しているのに、物価だけが上昇を続ける最悪の経済状態、「スタグフレーション」が国を覆う。
賃金は上がらず、人々の実質的な購買力は日々失われていく。年金生活者は、物価の上昇に追いつかない年金額に絶望するだろう。
最後の引き金
そして、最悪の事態が訪れる。国民の不満を背景に、政府が財源の裏付けもない大規模な減税や歳出拡大に踏み切った時だ。
市場は、この国が財政規律を完全に放棄したと判断する。2022年に英国を襲った「トラス・ショック」の悪夢が、このヒノモト群島国で再現されるのだ。
国債、通貨、株式が同時に暴落する「トリプル安」。それは、国家の信認が崩壊する音だった。
それは、毒を少しずつ飲み続けるような道だった。短期的な痛みはないかもしれないが、確実に死へと向かっていく。
第二章:信認という名の通貨
カイトは深くため息をついた。このジレンマの根源は、中央銀行の存在意義そのものに関わっている。
伝統的な経済学の教科書によれば、自国通貨を発行できる中央銀行は破綻しない。理論上は、無限にウヲを刷って債務を支払えるからだ。過去には、債務超過に陥りながらも通貨の信認を保った海外の中央銀行の例もある。
しかし、カイトはその理論の危うさを感じていた。現代の通貨の価値を支えているのは、金(ゴールド)でもなければ、政府の強制力だけでもない。
それは、「信認」という名の、目に見えない脆いガラス細工のようなものだ。
中央銀行が自らの財務悪化を恐れて、インフレを退治するための利上げができないと市場に見透かされた瞬間、その信認は崩壊する。中央銀行の独立性は失われ、政府の赤字を埋めるための機関、すなわち「財政ファイナンス」の実行者と見なされるだろう。そうなれば、ウヲの価値は暴落し、制御不能なインフレが人々を襲う。
「我々は、自らが作り出した怪物に喰われようとしているのかもしれない」
カイトは呟いた。異次元緩和という怪物は、デフレという竜を退治するために生み出された。しかし、あまりに長く野放しにされた結果、今や主人の喉元に牙を突き立てている。
終章:綱渡りの道
結局のところ、中央銀行が選ぶ道は、シナリオAでもBでもないだろう。その中間に存在する、一本の細い綱の上を渡るような、危険極まりない道だ。
経済指標を睨みながら、半年に一度、0.25%という、市場を刺激しないよう細心の注意を払った、極めて緩やかな利上げ。それは、シナリオAの激痛を避けつつ、シナリオBの破局からも逃れようとする、苦肉の策だ。
しかし、その綱渡りが成功する保証はどこにもない。あまりに遅いペースは、結局は信認の喪失を招くかもしれない。少しでも速めれば、経済が奈落の底へ落ちる。そして何より、その綱を支えているのは、信頼できる財政再建への政府の固い意志という、今この国で最も見出しがたいものなのだ。
カイトは二つのファイルを閉じ、デスクに置いた。窓の外では、首都の灯りが一つ、また一つと灯り始めていた。
あの無数の光の下で暮らす人々は、自分たちの未来が今、いかに危うい均衡の上にあるかを知らない。
静寂の淵に立つこの国で、中央銀行の苦悩は、まだ始まったばかりだった。