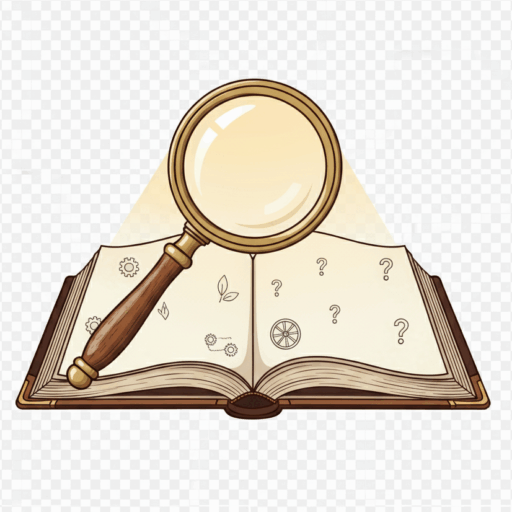かつて「論破」を聖戦と信じ、スマホを聖剣としていた田中誠(35歳、アカウント名:田中誠(リハビリ中))は、賢者ハトヤマとの対話を経て、己の過ちに気づいた。彼が振り回していた「寛容のパラドックス」は、諸刃の剣。使い方を誤れば、自分が一番不寛容な怪物になるということを、身をもって(そしてフォロワー数の激減をもって)学んだのだ。
彼は過去の自分の投稿を巡礼し、謝罪と対話を繰り返す中で、血と涙と恥ずかしい思い出から、三つの輝く神器を鍛え上げた。それが、新生・田中誠を支える「寛容の三種の神器」である。
- 一つ、真実を見極める「批判的思考の盾(クリティカル・シンキング・シールド)」
- 二つ、他者の靴を履く「視点取得の千里眼ゴーグル(パースペクティブ・ゴーグル)」
- 三つ、対話の橋を架ける「アイメッセージの宝玉(ほうぎょく)」
ある日のこと。田中のタイムラインに、典型的な炎上誘発ツイートが流れてきた。
「最近の若者はなってない!俺たちの時代はもっと根性があった!」
――古のインターネットから蘇ったゾンビのようなテンプレ投稿だ。
かつての田中なら、アドレナリン全開で「あなたの時代の根性論が今の社会問題を…」と100ツイートくらいのリプライ爆撃を敢行していただろう。
だが、今の彼は違う。
まず、彼は「批判的思考の盾」を構えた。盾はキラリと光り、投稿の裏に隠された投稿者の意図や、アルゴリズムの思惑を映し出す。
「この投稿は…怒りの感情に訴えかけ、エンゲージメントを稼ぐのが目的だな。ここで反応すれば、プラットフォームの思う壺だ」
彼は、怒りの感情に身を任せることなく、衝動的な反応をぐっとこらえた。盾は、彼の精神を無益な争いから守ったのだ。
次に、彼は恐る恐る「視点取得の千里眼ゴーグル」を装着した。
すると、投稿者の姿がぼんやりと見えてきた。社会の変化に取り残された不安、自分の価値観が通用しなくなった焦り、誰かに認められたいという孤独感。ゴーグル越しに見えるのは、憎むべき「敵」ではなく、社会の変化に戸惑う一人の人間だった。
「なるほど…この人は『若者を攻撃したい』のではなく、『自分の生きてきた時代を肯定してほしい』のかもしれない」
もちろん、だからといって彼の意見に同意するわけではない。だが、攻撃する気はすっかり失せていた。それでも、何かを伝えたい。そこで彼は、最後の神器、「アイメッセージの宝玉」をそっと取り出した。
田中誠(リハビリ中):「突然のコメント失礼します。そのように感じられるのですね。私は、あなたの投稿を読んで、世代間の価値観の違いについて改めて考えるきっかけをいただきました。私が今の社会で働いていて感じるのは〇〇という点なのですが、もしよろしければ、あなたが『根性があった』と感じる時代の具体的なエピソードをもう少しお聞かせいただけないでしょうか? 私は、あなたの経験から学べることがあるかもしれないと感じています」
主語を「あなた(You)」から「私(I)」へ。断罪から質問へ。宝玉の力は、一方的な攻撃を、相互理解への小さな一歩に変えたのだ。
相手からの返信は、意外にも穏やかなものだった。そこから、ぎこちないながらも対話が始まった。
今の田中は、もうネットのジャンヌ・ダルクではない。彼は、荒れ果てたデジタル世界の片隅で、対話という名の小さな苗を植える、しがない庭師だ。
彼は今でも、かつての自分のような「正義の十字軍」が、生半可な知識を振りかざして暴れているのを見かける。彼らは、自分がアルゴリズムに踊らされているだけの道化であることに気づかず、「論破!論破!」と叫んでいる。
その姿は、田中にとって過去の自分を映す鏡であり、赤面せずにはいられない黒歴史のタイムカプセルだ。
彼はもう彼らを辱めようとは思わない。なぜなら、彼らが一番辱められているのは、誰かに打ち負かされる時ではなく、自分の信じる「正義」が、実は誰かの手のひらの上で転がされているだけだと気づかない、その無自覚さそのものだからだ。
田中はそっとスマホを置き、思う。
寛容とは、相手を許すことではない。まず、反射的に相手を裁こうとする自分自身を、一度押しとどめる力なのだと。三種の神器は、そのための道具に他ならない。
そして彼は、今日もまた、新たな苗を植えるべく、静かにタイムラインを耕し続けるのだった。