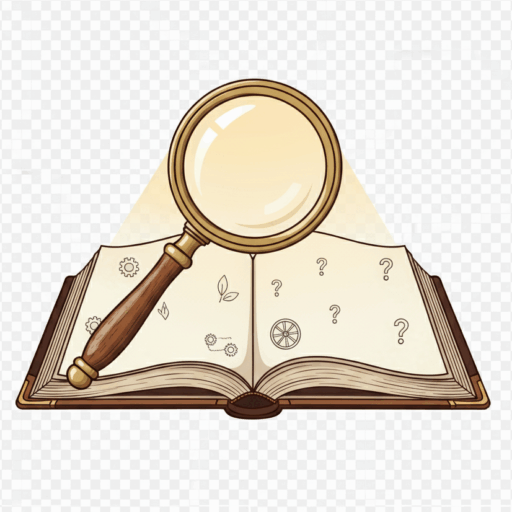最近、ニュースを賑わせている「過去最高の税収」と、それに続く「国民への還元」という言葉。一見すると、私たちの生活が楽になるような、喜ばしい話に聞こえます。でも、経済学者の端くれとして、私の頭の中では警報が鳴り響くのです。「そんなうまい話、本当にあるのだろうか?」と。
この違和感の正体を突き止めるため、私はペンを取ることにしました。これは、聞こえの良い政治スローガンの裏に隠された、不都合な真実をたどる、私の個人的な調査記録です。
疑問①:「過去最高の税収」は、本物の「余剰金」なのか?
まず、疑問の出発点である「過去最高の税収」から。財務省のデータを見ると、確かに2023年度の税収は72.1兆円と、4年連続で過去最高を更新しています。しかし、その中身を覗いてみると、手放しでは喜べない実態が浮かび上がってきます。
税収増の最大の立役者は、皮肉にも私たちの生活を苦しめている「インフレ」です。モノの値段が上がれば、その10%である消費税の額も自動的に増えます。企業も、物価上昇に合わせて賃上げをすれば、社員が払う所得税が増えます。企業の売上も名目上は膨らむので、法人税も増える。所得税、法人税、消費税。この主要三税が国税収入の8割以上を占めているのですから、インフレが税収を押し上げるのは当然の帰結です。
さらに厄介なのは、私たちの税制が持つ「増幅装置」の存在です。経済学の言葉で「税収弾性値」と呼ばれるこの仕組みは、名目GDPが1%成長すると、税収はそれ以上に、例えば1.14%増えるという性質を持っています。インフレで経済が見かけ上、膨らむと、税収はそれ以上にグンと伸びる。これが、実態以上の「財源がある」という幻想を生み出す元凶なのです。
つまり、今の税収増は、日本経済が力強く成長した証ではなく、インフレによって生じた、いわば「見せかけの好景気」の副産物に過ぎません。これを本物の「余剰金」と考えるのは、あまりにも早計ではないでしょうか。
疑問②:入るお金が増えたなら、出ていくお金はどうなっている?
コインに裏表があるように、インフレは政府の「収入」を増やす一方で、その「支出」も同じように、いえ、それ以上に膨らませます。この点が見過ごされがちな、最大の罠かもしれません。
例えば、道路や橋を造る公共事業。そのコストの基準となる「公共工事設計労務単価」は、13年連続で上昇を続け、直近ではインフレ率を大きく上回る5.9%もの伸び率を記録しています。防衛費も、装備品の高度化や円安による輸入価格の高騰で、前年度から6兆円も増加しました。
そして、最も見えにくい、しかし深刻なコスト増の仕組みが、地方財政との連動です。国家公務員の給与が民間の賃上げを反映して上がると、それに倣って全国の地方公務員の給与も上がります。警察官、消防士、学校の先生、市役所の職員…彼らの人件費が増えれば、その分を補うために国から地方へのお金、つまり「地方交付税」を増やさなければなりません。これは法律で定められた計算式で自動的に決まる、いわば「義務的な支出」なのです。
収入は一時的なインフレ頼み、支出は人手不足や制度に根差した構造的な要因で増え続ける。この現実を直視すれば、「増えた分を還元しよう」という発想がいかに危ういか、見えてくるはずです。
疑問③:それでも「減税」を叫ぶ政治家たちの思惑は?
この厳しい財政状況を前に、政治の世界ではどんな議論がされているのでしょう。調べてみると、驚くほど多くの政党が、党派を超えて「減税」を競い合っているのが現状です。
一時的な税収増を根拠に、毎年数兆円もの財源が必要な「恒久的」な減税をしすることは、打ち出の小槌を見つけたと思って、その小槌自体を叩き壊すような行為に他なりません。
最終結論:減税の先に待つ、私たちの未来
では、もしこのまま減税競争が進んだら、私たちの国はどこへ向かうのでしょうか。ここから先は、少し怖い話になります。
減税で歳入が減り、歳出は増え続ける。その差額は、当然「新たな借金」、つまり赤字国債の発行で埋めるしかありません。
問題は、その国債を誰が買うのか、です。これまでのように日本銀行が簡単に買ってくれる時代は、インフレの到来とともに終わりを告げました。市場の投資家たちは、日本の財政を厳しく見ています。すでに、日本の長期金利はじわじわと上昇を始め、市場が「警告」を発しているのです。
ここで無謀な減税に踏み切れば、どうなるか。日本の財政への信認が失われ、国債が売られる(=金利が急騰する)。すると円の価値が暴落し、輸入に頼る私たちの国の物価はさらに高騰する。まさに、2022年にイギリスで大規模減税策が金融市場の混乱を招いた「トラス・ショック」の二の舞です。
ここまで調べてきて、最初の違和感の正体がはっきりとしました。過去最高の税収とは、インフレがもたらした「砂上の楼閣」でした。そして「増収分の還元」という甘い言葉は、その楼閣の足元で、すでにもっと大きな穴が開き始めている現実から、私たちの目を逸らさせるための呪文だったのです。
政治家が選挙のために有権者の歓心を買うのは、ある意味で当然のことかもしれません。しかし、そのために未来の世代にツケを回し、国の信認を危険に晒す権利は誰にもないはずです。本当に私たちの生活を思うなら、今なすべきは、一時的な見せかけの「お小遣い」を配ることではなく、この国の財政という、私たちの生活の土台そのものを、静かに、しかし着実に修復していくことではないでしょうか。