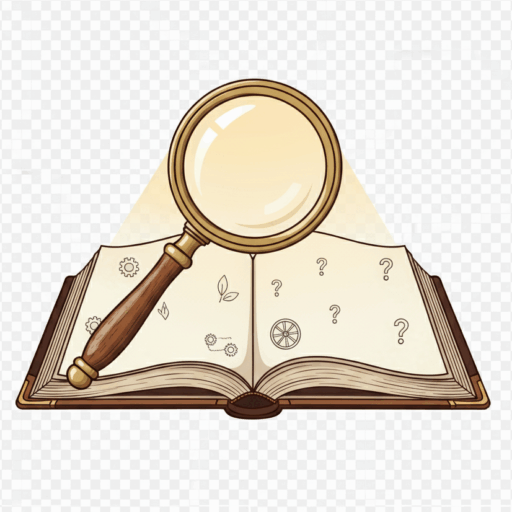ユウキくん:博士、こんにちは! テレビで見たんだけど、「不況の時は、政府がもっとお金を使えば景気は良くなる!経済の教科書にもそう書いてある!」って言っている人がいたんだ。それって本当なの?
博士:やあ、ユウキくん。いい質問だね。その主張は、ある意味では正しい。実際に、経済学の教科書には、不況の時に政府が公共事業を増やしたり減税したりすれば、経済が成長すると書かれていることが多い。
ユウキくん:やっぱりそうなんだ! じゃあ、どんどん政府がお金を使えば、僕たちのお給料も増えるってこと?
博士:そう単純な話ではないのが、経済の面白いところであり、難しいところでもあるんだ。その「教科書」が書かれた時代の経済と、今の日本とでは、決定的に違う『大前提』があるんだよ。
ユウキくん:大前提?
博士:うむ。その教科書が想定しているのは、「世の中には働きたい人がたくさんいて、人手には困らない」という社会だ。つまり、人口が増えていて、若い労働力がどんどん市場に入ってくるような時代をモデルにしているんだ。
ユウキくん:働く人がたくさんいるかどうか…それって、そんなに大事なことなの?
博士:ものすごく大事だよ。その前提が結論に大きな影響を与えるんだ。例えるなら、「水をたくさん飲めば健康に良い」という話も、「喉が渇いている人」という前提があってこそだろう? 砂漠で遭難している人には命の水でも、お腹を壊している人には毒になりかねない。
ユウキくん:なるほど…。
博士:昔の日本や、教科書が書かれた頃の国々は、まさに「労働力」という名の水が豊富にあった。だから、政府が「ダムを作るぞ!」と号令をかければ、「待ってました!」とばかりに働きたい人が集まり、それが所得になり、消費に回り…と、経済がスムーズに大きくなった。これを「乗数効果」と呼ぶんだ。
ユウキくん:ふむふむ。
博士:じゃあ、今の日本はどうかな? ユウキくんもニュースで聞かないかい? 「人手不足が深刻だ」とか。
ユウキくん:あ、聞く聞く! コンビニやレストランのアルバイト募集の貼り紙もすごいし。
博士:その通り。今の日本は、世界でも例を見ないスピードで人口が減り、高齢化が進んでいる。つまり、教科書の大前提だった「潤沢な労働力」が、もはや存在しないんだ。むしろ労働力は希少な資源になっている。
ユウキくん:前提が真逆なんだ!
博士:そうなんだよ。この前提の違いが、政策の効果を全く変えてしまう。
ユウキくん:どういうこと?
博士:まず、消費への影響だ。社会の高齢者の割合が高まると、人々は将来への不安から、政府からお金をもらってもすぐに使わず、貯蓄に回す傾向が強くなる。すると、昔のように「支出が次の支出を呼ぶ」という乗数効果が弱くなってしまうんだ。
ユウキくん:せっかくお金を配っても、みんなが貯金しちゃうと景気は良くならないもんね。
博士:そして、もっと深刻なのが生産への影響だ。人手不足の状況で、政府が「公共事業を増やすぞ!」と言っても、どうなるかな?
ユウキくん:えーっと…働く人がいないから、仕事が進まない?
博士:それもあるし、限られた働き手を建設会社やIT企業が奪い合うことになる。すると、人件費が高騰し、それが製品やサービスの価格に上乗せされる。結果として、経済の規模(作られるモノやサービスの量)はたいして増えないのに、物価だけが上がってしまうという事態になりかねないんだ。
ユウキくん:うわぁ…。良くなるどころか、ただ物価が上がるだけになっちゃうのか。
博士:そういうリスクがある、ということだね。つまり、「労働力が潤沢」という前提が崩れた現代日本では、教科書通りの財政出動は、かつてのような効果を発揮しにくくなっている。これが、冒頭の論説が指摘していることの核心なんだ。
ユウキくん:すごくよくわかったよ! 前提が違うと、同じ薬でも効かなくなるってことなんだね。じゃあ、今の日本はもう打つ手なしなのかな…?
博士:いや、そんなことはないよ。多くの経済学者や専門家は、この新しい現実を踏まえた上で、新しい処方箋を考えている。例えば、ただ需要を増やすのではなく、人手不足を補うためのロボット開発やDX(デジタル化)への投資のように、経済の供給能力そのものを高めるようなお金の使い方(賢い支出)が重要だと言われている。
ユウキくん:なるほど! お金の「量」だけじゃなくて、「使い方」が大事なんだね。
博士:その通り。古い地図で今の山を登ろうとすれば道に迷ってしまう。人口が減っていくという、今の日本の現実に合った新しい地図を描くことが、我々に求められているんだよ。