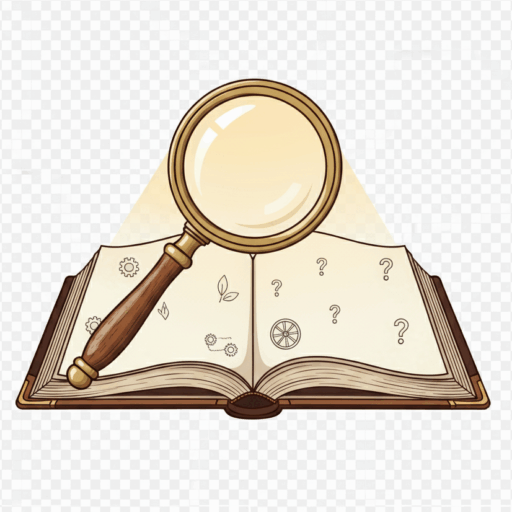第一章:帰郷
東京のコンサルティング会社で働く俺、長谷川健太は、無機質な数字とグラフだけが支配する世界に生きていた。クライアント企業のコストを1%削減し、利益率を0.5%向上させる。それが俺の仕事であり、価値だった。だから、母からの電話で祖父が倒れたと聞いた時、頭に浮かんだのは心配よりも先に「非効率」という言葉だった。
「健太、お願いだから一度帰ってきて、じいちゃんを説得しておくれ。もう年なんだから、あの田んぼは無理だよ」
受話器の向こうで嘆く母の声を背に、俺は重い腰を上げた。北陸新幹線に乗り込み、車窓を流れる景色がビル群から田園風景に変わるにつれ、苛立ちは募った。
祖父、清一が暮らすのは、山の斜面に沿って小さな田んぼが幾何学模様を描く、いわゆる中山間地域だ。子供の頃は夏休みの楽園だったが、今の俺の目には、生産性の低い零細農地の典型にしか映らない。祖父は役場を定年退職した後、先祖代々の数枚の棚田で米を作っているが、収支は火を見るより明らかだった。農機具の維持費、肥料代、そして膨大な時間。持ち出しであることは間違いない。
「じいちゃん、もうやめよう。この田んぼは、もっとうまくやれる人に任せるべきだよ」
数年ぶりに会った祖父は、縁側で痩せた背中を丸めていた。俺の言葉に、清一はゆっくりと顔を上げ、深い皺の刻まれた目で俺を見つめた。
「健太、おめえには分からんかもしれんがな。この田んぼは、ただ米を作るだけの場所じゃねえんだ」
その言葉は、俺のロジックを拒絶する、古い世代の感傷にしか聞こえなかった。
滞在中、俺は高校の同級生で、今やこの地方で最大規模の農業法人を経営する拓也に連絡を取った。拓也の農場は平野部にあり、その光景は圧巻だった。GPSで自動走行する巨大なトラクター、ドローンがリアルタイムで生育状況をセンシングし、AIが最適な肥料散布量を計算する。
「うちはもう、国内だけじゃなく海外にも販路を広げてる。特にヨーロッパや東南アジアの富裕層に、うちのブランド米は人気でね。農業もこれからはデータと戦略だよ」
拓也の言葉に、俺は我が意を得たり、と頷いた。これこそが、日本の農業が生き残る道だ。非効率な中小の兼業農家は淘汰され、拓也のような競争力のある経営体に集約されるべきなのだ。俺は、祖父を説得する材料が揃ったと確信した。
第二章:見えない価値
村を歩くと、拓也の農場とは対照的な風景が広がっていた。手入れの行き届いた祖父の棚田の隣には、セイタカアワダチソウが人の背丈ほどに伸びた耕作放棄地が広がっている 3。高齢化と後継者不足。数字でしか見ていなかった問題が、生々しい現実として目の前にあった。
「昔は、村のみんなで水路の掃除も、畔の草刈りもやったもんだがのう」
通りがかった古老が、杖を突きながら寂しそうに言った。
その夜、天気予報が「これまでに経験したことのないような大雨」を告げた。夜半から降り始めた雨は、バケツをひっくり返したような豪雨となった。スマートフォンの画面には、下流の町の河川が危険水位に達したという警告が何度も表示される。俺は、この古い家が土砂崩れに巻き込まれるのではないかと、本気で恐怖を感じた。
夜が明け、雨脚が少し弱まった頃、俺は恐る恐る外に出た。村の中を流れる小川は濁流と化していたが、氾濫はしていない。そして、俺は信じられない光景を見た。
眼下に広がる棚田という棚田が、なみなみと水を湛え、巨大な貯水池のようになっていたのだ。一枚一枚の田んぼが、斜面を流れ落ちる水の勢いを食い止め、少しずつ、少しずつ、下流へと流している。まるで、緑のダムだ。
「じいちゃん…これ…」
いつの間にか隣に立っていた清一に声をかけると、彼は静かに頷いた。
「田んぼはな、米を作るだけじゃねえ。こうやって水を貯め、土砂が崩れるのを防ぎ、俺たちの暮らしを守ってくれてるんだ。お前らが住む下流の町もな、この田んぼがあるから、大きな水害にならずに済んでるんだぞ」
その言葉は、俺の胸に重く響いた。コスト、利益率、生産性…俺がこれまで信奉してきた指標では測れない価値が、そこにはあった。農業が持つ「国土保全」という公共性。それは、俺のビジネスの世界では「外部経済」と呼ばれる、市場価格には決して反映されない恩恵だった。
第三章:二つの未来
数日後、俺は再び拓也に会った。豪雨の話をすると、彼は意外なことを言った。
「健太、俺も分かってるんだ。俺たちが平野部で効率よく農業ができるのは、清一さんみたいな人たちが、あの山の上で必死に田んぼを守ってくれているおかげでもあるんだ。あそこが崩れたら、俺たちの農地だって無事じゃ済まない」
拓也は真剣な目で続けた。
「俺の役割は、日本の農業を『産業』として世界と戦えるレベルに引き上げること。でも、清一さんたちの役割は、この国の『国土』を守り、俺たちの足元を支えること。どっちが偉いとか、どっちが正しいとかじゃない。両方必要なんだよ」
拓也の言葉は、俺の中でバラバラだった二つの風景を一つに繋げた。効率を追求する平野部の巨大農場と、多面的な機能を担う中山間地域の棚田。その両方が、互いに支え合いながら日本の農業を、そして俺たちの生活を成り立たせている。
俺は、祖父の米作りを「非効率」の一言で切り捨てようとした自分を恥じた。東京で俺が享受している安全な水、豊かな食、災害の少ない暮らしが、この名もなき農村の、利益度外視の営みによって支えられているという事実に、ようやく気づいたのだ。
実家を発つ日、俺は清一に頭を下げた。
「じいちゃん、ごめん。俺、何も分かってなかった」
清一は何も言わず、ただ俺の肩をポンと叩いた。
東京に戻る新幹線の中、俺はノートパソコンを開き、新しい企画書のタイトルを打ち込んだ。『中山間地域の多面的機能の価値評価と、都市住民による新たな支援モデルの構築』。週末は、田舎に帰ろう。そして、俺にしかできないやり方で、この国の風景を守る手伝いをしよう。
車窓から見える夕日に染まる棚田は、今まで見たどんな景色よりも美しく、そして尊く見えた。それは、米だけでなく、水と、土と、そこに生きる人々の未来を育む、希望の風景だった。